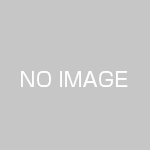この記事は2020年6月に配布した顧問企業法務通信から抜粋したものです。
いつも、ご相談、ご活用いただき、ありがとうございます。
今回は、業務委託の限界というテーマで書かせていただきました。
昨今のコロナ禍、事業者様のなかには、思うように営業ができない反面、時間ができたということで、様々な取引関係の見直しや契約書類の整備を図られる方もすくなくないようです。
先日は、私も、新規ご相談者様から、曖昧になっている会社とスタッフの契約関係について、契約書類を作成することで、従業員ではなく個人事業主として扱うことはできないか、というご相談をお受けしました。
業界によっては、雇用(従業員)でなく業務委託(外注・個人事業主)として扱うことが、業界慣行やそれぞれの希望に沿うこともすくなくないようです。
また、コロナ禍のような事態でやむなく会社がスタッフへ支払をしないという判断をする際、一般的に、雇用より業務委託の方が正当化しやすいでしょう。
しかし、雇用(従業員)か、業務委託か(外注・個人事業主)という問題は、労使、税務や社会保険(労働保険)と密接に関連しており、実際にトラブルになった場合、「業務委託だから」の一言で片づけられるものでもありません。
もちろん、個人事業主という働き方を否定する趣旨ではなく(ちなみに、私も個人事業主です)、予めその限界をきちんと知っておくことが重要だと思います。
【1 業務委託契約書を交わしておけばよい?】
【2 業務委託ではなく雇用だと判断されたら】
【3 雇用か業務委託かの判断要素】
【1 業務委託契約書を交わしておけばよい?】
契約書は有用ですが、取引の実態で実質的に判断されます
(きちんとした契約書を交わすことは有用です)
通常、契約関係が曖昧になりそうな場合に役に立つものが契約書です。
もし将来雇用か業務委託かが問題となった際は業務委託であると主張したいと考えている場合、これに備えて予め業務委託契約書を交わすことは、通常、とても有用だと思います。
なお、ただ「業務委託契約書」という表題の契約書を交わすだけではなく、雇用ではなく業務委託(請負契約または準委任契約)であると法的に評価されるような内容になっている必要があります。
(雇用か業務委託かは取引の実態で実質的に判断されます)
契約書の内容と取引の実態が乖離していると、トラブルの原因となります。
特に、雇用か業務委託かという問題は、労使、税務や社会保険(労働保険)と密接に関連しており、場合によっては、労使では労基署や裁判所が、税務では税務署が、社会保険(労働保険)では労基署が、判断することになります。
そして、判断される際は取引の実態で判断されますので、契約書を交わしていなかった場合はもちろん、業務委託契約書を交わしていた場合でも、「業務委託だから」の一言では片づけられないこともすくなくありません。
取引の実態のどのような要素に着目するか、詳細は後述しますが、業務上、指示に対する諾否の自由の有無、指揮監督の程度の強弱、勤務場所や勤務時間の拘束の有無など、スタッフが会社へ従属しているかどうかで判断されます。
(雇用か業務委託かが特に問題となる場面や業種)
労使では、会社がスタッフへ一方的に契約終了を通知した場合や、会社の業務中にスタッフが怪我をしてしまった場合が考えられます。
税務では、会社がスタッフへ支払っていた費用を消費税課税仕入としていた場合や、会社がスタッフからの源泉徴収をしていなかった場合です。
社会保険(労働保険)では、アルバイト1名のみの採用で会社が労災保険に未加入だった場合や、その状態で業務中に怪我をしてしまった場合です。
業種としては、例えば、美容室、整骨院、マッサージ、接客を伴う飲食店、保険代理店、不動産仲介業などですが、従業員扱いと個人事業主扱いが混在している業種であれば、どこでも問題になりやすいのではないかと思います。
【2 業務委託ではなく雇用だと判断されたら】
給与、税金、労働保険料など、相応の負担となることがあります
(労使について)
労使では、会社がスタッフへ一方的に契約終了を通知した場合や、会社の業務中にスタッフが怪我をしてしまった場合が考えられます。
このような場合、ときには、スタッフが、労基署や裁判所(合同労働組合や弁護士)の助力を得て、会社へ、給与や慰謝料を請求することがあります。
まさしく業務委託であれば、一方的な契約終了も原則可能であり(契約内容によるが、請負につき民法641条、準委任につき民法651条1項)、業務中の怪我について、事案によりますが、会社はスタッフへ損害賠償責任を負わないとされることも多いでしょう。
しかし、取引の実態から雇用であると判断された場合には、話が変わります。
すなわち、雇用と判断された場合、一方的な契約終了は、原則として無効とされますので(労働契約法16条、有期契約につき労働契約法19条)、通常の不当解雇と同様に、契約終了通知後も報酬(賃金)が発生してしまいます。
また、雇用と判断された場合、業務中の怪我について、会社は労基署へ労働災害として扱う必要があるほか、安全配慮義務違反による損害賠償責任を負い労災補償で填補されない慰謝料等の支払義務が発生することがあります。
(税務・社会保険(労働保険)について)
税務等は、税理士さん等の領域ですが、簡単に触れておきます。
例えば、会社がスタッフへ業務委託料として消費税を含めて支払ったうえで、会社が税務署へこれを課税仕入れとして確定申告していた場合、もし税務調査で雇用と判断されると、給与は課税仕入れとはならないため、修正申告が必要となり、遡ってかなりの金額の消費税が会社に課税されることがあります。
業種によって業務委託の源泉徴収義務がなく、源泉徴収していなかったのがもし雇用と判断された場合、源泉徴収分が会社に課税されることがあります。
また、会社が業務委託扱いのスタッフについて労災保険に未加入だった場合、もし労災調査で労基署に雇用と判断されると、労災保険の加入を求められたり、遡って労災保険料を支払うよう求められたりすることがあります。
さらに、会社が業務委託扱いのスタッフについて労災保険に未加入で業務上の事故が発生した場合、もし労災調査で労基署に雇用と判断されると、労基署がスタッフへ労災補償をしたうえで、労基署が会社に求償することもあります。
【3 雇用か業務委託かの判断要素】
取引(稼働)の実態に照らして従属性という観点から判断されます
(判断要素)
基本的な要素は以下のとおりです(括弧内は従属性肯定)※菅野労働法参照
・ 仕事依頼に対する諾否の自由の有無(自由なし)
・ 業務の内容や遂行の仕方について指揮命令を受けているか(受けている)
・ 勤務の場所や時間が規律されているか(規律されている)
・ 業務遂行を他人に代替させられるか(代替させられない)
以上に加えて、以下も考慮されます
・ 報酬の額、計算方法、支払形態が従業員と同質か(時給計算、最低保証)
・ 給与所得の源泉徴収の有無、労働保険料の徴収の有無等(徴収あり)
・ 専属的に従事しているか(他の会社で仕事をしておらず掛け持ち不可)
・ 設備機械の所有、経費の負担、剰余金の取得、部下の雇用など(なし)
いろいろな要素を挙げましたが、実際には会社やスタッフがどのように希望しているかという問題はあるものの、業務委託ではなく雇用の方がスタッフの保護される程度は高いので、スタッフの会社への従属性が高ければスタッフの地位を保護するという労働者保護的な判断に流れるものと思われます。
したがって、指示に対する諾否の自由がない、指揮監督が強い、勤務場所や勤務時間の拘束がある、時給計算や最低保証あり、専属(掛け持ち不可)等となれば、会社がスタッフの生殺与奪を握っているに等しいので、業務委託ではなく雇用としてスタッフが保護されることになるのではないかと思います。
なお、以上は、主に労使関係において雇用(従業員)か業務委託(個人事業主)かを判断する際の要素です。
以上は、税務等における判断に当然に妥当するものではありませんが、国税不服審判所の裁決等をみる限り、基本的な判断枠組は同様と考えられます。
(終わりに)
以上のように、雇用か業務委託かは取引の実態に照らして従属性という観点から判断されますし、業務委託扱いをしていたが雇用と判断された場合相応の経済的な負担となることもありますので、注意や準備が必要です。
リスクを考慮して、最初から雇用扱いとすることもありえます。
業務委託扱いとする場合、会社とスタッフの双方の身を守る方法として、会社から、スタッフへ、確定申告をさせる、所得補償保険や賠償責任保険に加入させる、労災保険に特別加入させる等の対応を検討してもよいと思います。